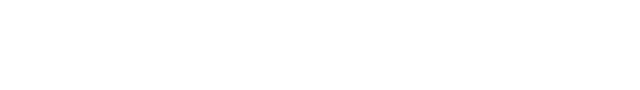睡眠時無呼吸症候群について
典型的な睡眠時無呼吸症候群 ( Sleep Apnea Syndrome:SAS ) では、ほとんどの人が大きなイビキをかき、途中でイビキが止まって静かになり、その後ため息とともにまた大きなイビキをかくということを繰り返す病気です。
多くの場合は同居する家族の方がイビキに悩まされ、配偶者も別室で寝るようになったりします。
そのうちに呼吸が長く止まっていることに気づくと心配になり本人にそのことを伝えます。
本人はそれほど鼾が大きいとは気づきませんが、自分のいびきで目が覚める人も珍しくはありません。
医療機関にかかると、まず症状を聞かれます。
大抵は質問票で昼間どのくらい眠いのかを確認されます。
エプワースのスコアという眠気のスコアを確認されます。
これで眠気が強いと判断されたら、簡易検査という比較的かんたんな検査を受けます。
この検査では一時間に何回呼吸が止まったり浅くなったりするかを大雑把に確認できます(これを無呼吸低呼吸指数:AHIといいます)。
浅くなったりと言いましたが、いびきをかくと呼吸での空気の入れ替えがだいたい半分以下に落ちてしまうから、呼吸は止まらぬまでも浅くなることも問題なのです。
AHIは正常では5未満です。
簡易検査でAHIが40以上であれば、すぐに治療を開始する必要があります。
しかしAHIが5以上、40未満の場合は終夜睡眠ポリグラフ検査(PSGといいます)を行う必要があります。
PSGは睡眠中の脳波を計測しながら、呼吸や心電図のモニタリングをおこなう大掛かりな検査で、かつては入院しなければできませんでした。
しかし
最近では自宅でできるPSGも開発されています。
このPSGでAHIが20以上の場合に治療を行うということが日本の健康保険のルールです。
睡眠時無呼吸症候群の治療法は、今の所持続陽圧呼吸療法しか選択肢がないのが実情です。
軽症の場合はマウスピースを作ったりする場合もありますが、AHIが20以上では持続陽圧呼吸療法がゴールデンスタンダードとされています。
睡眠時無呼吸症候群を放置すると、心房細動という脳梗塞の原因になる不整脈の頻度が2倍になるとされています。
イビキは周りがうるさいだけでなく、患者さんの将来の健康に関わる重大な合併症を起こすことがありますので治療は必須と言えます。
この他睡眠時無呼吸症候群の診療を行っておりますと、睡眠相の異常(体内時計が狂っている状態)や不眠の患者さんも必然的に増えてきます。
このためこれらの方のご相談・治療も引き受けております。